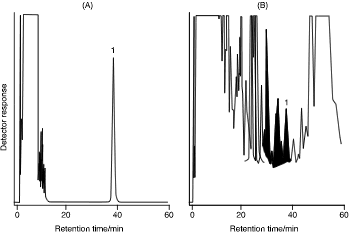実用的蛍光誘導体化
7
福岡大学薬学部
山口政俊・能田 均
6.チオール類の蛍光誘導体化
チオール基を有する生体成分にはシステイン、ホモシステイン、
グルタチオン、補酵素Aなどの低分子やシステインを含んだペプ
チド・タンパク質があり、それぞれ重要な機能に関与している。ま
た、チオール基を有する薬品やチオール類を含む食品も多い。チ
オール基は反応性が比較的高いので、しばしば蛍光誘導体化の対
象となる場合が多く、アミノ基と並んで他種類のチオール基用誘
導体化試薬が市販されている。生体試料の分析においては、一般
にアミノ基を含む化合物よりチオール基を含む化合物の方が少な
いので、チオール基を誘導体化する方が選択性は高くなる。チオー
ル基は酸化されやすく、容易にジスルフィド(-S-S-)体に変化する
ので、還元剤を加えて全てチオール基とした後に定量する場合も
ある。また、蛍光誘導体化反応中の酸化を抑えるために酸化防止
剤を加えて誘導体化することも多い。特に酸化されやすいチオー
ルを定量する場合や酸化性物質を含む試料を分析する場合には充
分な注意が必要である。
チオール基の蛍光誘導体化反応は、Fig.1に示す7種に分類でき
る。それぞれ特徴があり、チオール化合物や測定試料の性質に応
じて最適な反応を用いる必要がある。詳細は総説1) を参照されたい。
6.1. N-置換マレイミド(Fig.1 A)
N-置換マレイミドがチオールと容易に反応して、図のような付
加物を与えることは古くから知られていた。このRに蛍光性基(2
−フェニルベンゾイミダゾール)を導入すると、試薬自身は無蛍
光性となり、チオールと反応して生成した誘導体は蛍光性となる
ことが見いだされ、それ以降様々な蛍光性基を導入した試薬が開
発された。本反応は緩和な条件(室温、pH5〜9)で数分以内に
進行するので、熱に弱いチオール(ペプチドやタンパク質)の蛍
光誘導体化に汎用される。ただし、蛍光誘導体はさらに加水分解
を受けるので(図の括弧内の反応)、プレカラム誘導体化HPLCに
おいて複数のピークを与えることがある。反応温度を高くしたり、
時間を延長して加水分解反応を完結させた後に分析すると一本の
ピークとなることが多い。低分子のチオール類に適用される市販
試薬N-[4-(6-dimethylamino-2-benzofuranyl) phenyl]maleimideを用いた応用例がDOJINDOのカタログ(http://www.dojindo.co.jp/wwwroot/productsj/info2/07/dbpm.html)にある。
高分子(ペプチド、タンパク質)用の試薬としては、フルオレッ
セイン、各種ローダミン、シアニン色素等を蛍光性基として導入
したマレイミド試薬が市販されており、蛍光標識高分子の調製に
用いられる。これらの試薬はそれ自身も蛍光性を有するものが多
く、緩和な条件で蛍光誘導体化したのちにゲル濾過等で試薬と標
識高分子を分離する必要がある。一例としてシアニン色素−マレ
イミドをIgGの蛍光標識に利用した例がDOJINDOのカタログ (http://www.
dojindo.co.jp/wwwroot/productsj/info2/07/ic3-m.html)にあるので参照されたい。これらの試薬は励起波長が長
いので、レーザー光源を使った高感度化が可能である。
6.2. オルトフタルアルデヒド(OPA)と第一アミン(Fig.1 B)
OPAはアミン及びアミノ酸の誘導体化試薬として汎用されるが
(本連載2.1.参照)、図に示すようにOPAと第一アミンを試薬と
して用いることにより、チオールの蛍光誘導体化が可能となる。本
誘導体化反応は緩和な条件で1分程度で完了するので、プレカラ
ム誘導体化のみならずポストカラム誘導体化にも用いることが出
来る。生成する誘導体はやや不安定であるので、ポストカラム誘
導体化の方が高い精度を得やすいが、感度は低くなる。高感度と
高精度を同時に達成するために、プレカラム誘導体化を自動化し
た測定法2)も報告されている。
6.3. ベンゾフラザン(ベンゾオキサジアゾール)誘導体 (Fig.1C)
Rとしては、-NO2、-SO3 - NH4+、-SO2NH2
及び-SO2N(CH3)2がある。このうち反応速度が大きく、蛍光誘導体が最も安定な4-
フルオロ-7-スルファモイルベンゾフラザン(ABD-F)が有用で、 HPLCにおけるプレラベル誘導体化試薬として汎用されている。
反応は、50℃で5分間以内に完結する(応用例:DOJINDOのカ タログ、 http://www.dojindo.co.jp/wwwroot/productsj/info2/
07/abd-f.html)。ABD-Fを用いてホモシステイン等をプレカラム誘
導体化し、キャピラリー電気泳動-レーザー誘起蛍光検出により、
試料の微量化と高感度化が達成されている。3)
6.4. ヨードアセトアミド (Fig.1 D)
緩和な条件下(室温、中性〜弱アルカリ性)で、長時間(1〜12時
間)かけて反応させる場合が多い。Rとしては、クマリン色素、ピ
レン、フルオレッセイン及びローダミン色素類が用いられ、主に
高分子の蛍光標識に用いられる。マレイミド試薬に比べて反応は
遅いが、生成した誘導体は安定である。
6.5. アジリジン (Fig.1 E)
市販試薬にダンシルアジリジンがある。反応は弱アルカリ性
(pH8.2)下、60℃で1時間の加熱を要する。反応はマレイミド試
薬と同様に選択性が高く、生成した誘導体は安定で、かつ200nmに及ぶ長いストークスシフトを特徴とする(励起波長338nm、発光波長540nm)。
6.6. モノブロモビマン (Fig.1 F)
この試薬は、比較的緩和な条件下(室温、中性〜弱アルカリ性)
で数分間で反応が完結する。試薬自身は無蛍光性であるが分解しやすく、その分解物はHPLCにおいて複数のピークを与えるので、それらが定量を妨害する場合がある。
7.アルコール
アルコール性水酸基を有する化合物は生体や食品中に多いが、
この官能基は極めて反応性に乏しい。従って、蛍光誘導体化試薬
には高い反応性が要求され、一般にカルボン酸クロライドあるい
はその類縁物質が用いられる(Fig.2)。反応は一般に高温(80-120
℃)で長時間(30-60分)加熱する必要がある。試薬はいずれもそ
の高い反応性故にアミン、チオール、水などとも反応し、蛍光性
物質(分解物)を与えるので、試料の前処理や試薬溶液等の調製時
には留意する必要がある。試薬およびその分解物はアルコールの
蛍光誘導体と同様の蛍光特性をもつ場合が多いので、蛍光誘導体
化は専らプレラベル反応に用いられる。
7.1.ヒト皮表脂質中7-デヒドロコレステロール(7-DHC)の定量 4)
7-DHCは皮膚表面に存在し、光化学的にビタミンD 3に変換される。加齢とビタミンD3生合成能の関連を研究するため、皮表中
7-DHCが測定される。しかし、その濃度は極めて低いので、従来
は切除した皮膚組織を有機溶媒抽出し、その抽出液を試料とする
必要があった。より被験者の負担が軽いヒト皮表脂質(皮膚を切除
することなく、皮表から直接脂質を抽出)を試料として分析するこ
とが望ましい。
本法は、皮表脂質を特殊な抽出装置(Fig.3)を用いて抽出し、こ
れに含まれる7-DHCをDMEQ-CON3を用いて蛍光誘導体化し 、HPLC検出する。本法により初めて皮表脂質中7-DHCの定量が可
能となり、加齢とともに同7-DHC濃度が低下することを実証した。
Chart 1 Procedure for the determination of 7-dehydrocholesterol in
human skin surface
Human skin surface (2.25 cm2)
Extract with n-hexane-ethanol (1:1, v/v)(30ml) by an extraction device Extract
Evaporate under N2 gas
Reconstitute with acetone
mix
Evaporate under N2 gas
2.0 mmol/l DMEQ-CON3 0.2ml
Heat at 120℃ for 60 min
Dilute with methanol 1.8ml
mix
Apply onto HPLC (10μl)
HPLC conditions
Column:TSK gel ODS-120T(250×4.6mm i.d.;5μm)(50℃)
Mobile phase: aqueous 90%(v/v) acetonitrile
Flow rate: 1.0 ml/min
Fluorescence detection: Ex.360nm Em.440nm
|
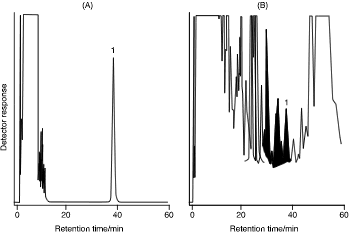 |
| Fig.4 Chromatograms obtained with (A) a standard solution and (B) an
extract of human skin (abdomen) surface. Peaks and concentrations: 1=7-DHC [A, 80.0 pmol
(30.7ng); 13.8pmol (5.29ng)cm-2 skin surface]; others=A, the reagent blank; B,
the reagent blank and endogenous substances in human skin surface. The shaded areas
disappeared upon oxidation and two peaks (in broken line) appeared. |
8.フェノール
フェノール性水酸基を有する化合物は生体中ではカテコールアミ
ン、セロトニン、チラミン、チロシンとがあるが、いずれもその水
酸基を誘導体化のターゲットとすることは少ない。しかし
、近年、環境中の内分泌撹乱物質としていくつかのフェノール類が注目され
ており、フェノール性水酸基用の蛍光誘導体化反応に関する研究も
盛んになっている。フェノール性水酸基は比較的反応性が高く
、アミノ基用の蛍光誘導体化試薬により誘導体化できる場合が多いが
、その中でも反応性の高い酸クロリド類が有用である。反応条件は
、アミンの場合と比べると、高温(50〜60℃)で長時間( 30〜60分)を要する。また反応中における試薬の加水分解を抑えるために
、反応液には出来るだけ水が入らないように前処理及び試薬溶液の調
製を行う。
参考文献
1) K. Shimada, K. Mitamura, J. Chromatogr. B, 659, 227 (1994).
2) S. K. Park, R. B. Boulton, A. C. Noble, Food Chem., 68, 475 (2000).
3) S. H. Kang, W. Wei, E. S. Yeung, J. Chromatogr. B, 744, 149 (2000).
4) T. Iwata, H. Hanazono, M. Ymamaguchi, M. Nakamura, Y. Ohkura Anal. Sci., 5,
671(1989).