 |
| トップページ > 「蛍光生物学」の最前線3 |
 |
|||||||||||||||
「蛍光生物学」の最前線3
1.量子ドットとは量子ドットは微小な空間内に電子を閉じ込めるために人工的に作られた蛍光性のナノ粒子で、サイズは通常 1-10 nm(1 nm=10 億分の 1 m)であり、以下のようないくつもの特徴と有機系の蛍光色素にはない優れた利点を持っている。
このような優れた特性を併せ 持つ量子ドットをバイオ分野で生体分子や生体組織を可視化するための蛍光プローブとして活用するための研究が近年盛んに行われている。  量子ドットを用いた in vitro バイオイメージング細胞膜を構成する重要な生体分子である糖タンパク質や糖脂質は糖鎖と呼ばれる分子がその末端に化学的に結合している。そのために細胞接着に加え、細胞の外部からの情報を細胞の内部に伝えるレセプター分子やアンテナ分子として生命活動において重要な役割を担っている。糖鎖の構造は細胞の種類によって異なり、細胞が分化したり、がん化によって変異したりした場合にも変化することが知られている。この糖鎖の構造の違いを厳密に識別して、結合するタンパク質がレクチンである7,8)。レクチンは植物の種子や動物の組織からこれまでに数多く見出され、その多くは構造も明らかにされている。また、結合する糖鎖の構造や種類によっていくつかのグループにも分類されている。我々は量子ドットとレクチンを用いた細胞標識技術の開発を目的として、まず白血病細胞のみを凝集するレクチンのスクリーニングを行った。その結果、大豆凝集素(soybean agglutinin、以下、SBA)が白血病細胞のみを特異的に凝集することを見出した。次に紫外線を照射した場合に緑色の蛍光を発する量子ドット(サイズは 3 nm)をジメルカプトコハク酸で表面修飾することにより、表面をカルボキシル基で覆われた水溶性溶媒に対して優れた分散能を持つ量子ドット(以下、QD)を調製することに成功した。この両者を 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩を用いた脱水縮合反応により、SBA の周りに QD が結合した QD 標識 SBA(以下、QD-SBA)を調製した。この QD-SBA を Jurkat と呼ばれる株化白血病細胞の培養液中に添加して培養した後、蛍光顕微鏡で観察したところ、Jurkat 細胞が鮮やかな緑色の蛍光を発していた(図2(A))。一方、同様の操作を健常な人から採取した白血球細胞で行った場合には緑色の蛍光は全く観察されなかった(図2(B))。これらの結果はレクチンの分子認識機能、すなわち、SBA が白血病細胞だけに存在する細胞表面の糖鎖を認識して結合するという分子認識機能を反映したものである5)。この技術を糖鎖に対する特異性の異なる別の種類のレクチンに応用することにより、他の様々な細胞についても変異や分化の様子を簡便に、そして正確に調べることも十分に可能であると考える。今回の実験では比較のために量子ドットに加えて、有機系の蛍光色素であるフルオロセインイソチオシアネート(以下、FITC)で蛍光標識した SBA と、正常な白血球細胞にも反応する小麦胚芽凝集素(以下、WGA)も用いた。まず、FITC-SBA では QD-SBA の場合と同様に緑色の蛍光を発する Jurkat 細胞は観察されたが、その蛍光の強さは QD-SBA に比べて非常に低いことが分かった(図2(C))。一方、QD-WGA は正常な白血球細胞にも反応するため、白血球細胞は緑色の蛍光を発していた。また、QD-SBA を Jurkat 細胞に添加して 6 時間経過すると、Jurkat 細胞内の蛍光量が増加している様子が観察された(図3(A))。これは量子ドットを用いることにより、SBA のようなレクチン質分子が細胞質内に取り込まれていく様子を高感度にリアルタイムで観察することも可能であることを示唆している。さらに長時間培養すると、凝集した細胞やアポトーシス様の細胞死が誘導された細胞などを観察することもできた(図3(B))。量子ドットで標識したレクチンを用いてグラム陰性菌を検出した例もいくつか報告されている9,10)ので、引用文献を参照して頂ければと思う。  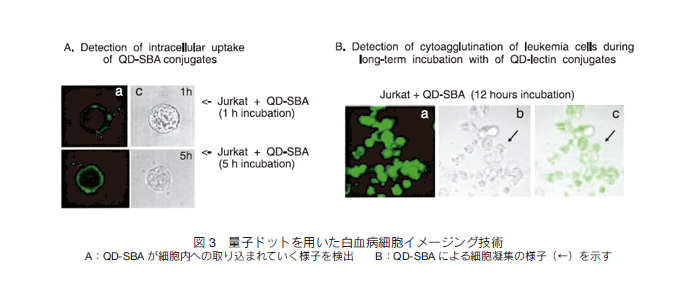 3.量子ドットを用いた in vivo バイオイメージング 現在、がんの性質(悪性度)診断や転移、再発巣の診断として有用性が高い検査手法として広く汎用されているのが、ポジトロン CT(以下、PET)である。PET はグルコースに目印となるポジトロン核種を合成した薬剤、放射性ブドウ糖擬似物質 F-18-fluoro-deoxy-glucose、を被験者に静注し、一定時間後にその体内分布を特殊なカメラで映像化する診断法である。最近では単なるがんの診断法としてだけではなく、薬物の体内動態や組織のエネルギー代謝を調べる技術としても応用されており11)、その有用性が高く評価されている。しかし、検査には放射性物質を使うことから、放射線被爆が大きな問題となっている。この点において、光は非侵襲であり、かつ高感度であるため、病気の診断に応用できる可能性がある。はじめに述べたように高い蛍光強度と強い耐光性という特性を併せ持つ量子ドットを利用して、生体内でがん細胞や組織のイメージングを行う試みは既に始まっている。代表的な例としては量子ドットで蛍光標識した前立腺特異的膜抗原に対する抗体をマウス尻尾の静脈に注射し、一定時間経過した後に紫外線を照射することにより、前立腺がんを検出した報告12)がある。また、転移性乳がんの抗がん剤である抗 HER2 モノクローナル抗体を量子ドットで標識化したものを、HER2 発現乳がんを埋め込み腫瘍に成長させたマウスの尻尾の静脈に注射後、腫瘍内に集積した量子ドットを追跡することに成功したことも報告されている13)。生体の場合は呼吸や血流に伴った振動や生体内からの自家蛍光に起因して蛍光シグナルが低下する可能性がある。しかし、量子ドットの中には近赤外部の波長領域まで蛍光を有するものも開発されているため、これを利用すれば皮膚や組織の自家蛍光と区別するのが容易となる。加えて、一励起波長で同時多色観察ができるため、工夫すれば数種類のがんの診断を同時に行うことも可能になると考える。今後、このような基礎的な研究データが蓄積されると共に、量子ドットそのものの体内動態や毒性等の問題が解決されれば、量子ドットを使った診断技術が近い将来 PET の代替法として実用化される可能性も充分にあると考える。 4.まとめ 生体内では日夜様々な生体分子が機能している。これらの個々の生体分子の役割を機能している“その場”で、精度良く、そして客観的に明らかにすることは生命科学研究の大きな目標のひとつである。
|
|||||||||||||||
| Copyright(c) 1996-2011 DOJINDO LABORATORIES, ALL Rights Reserved. |
