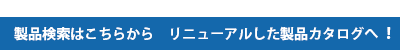地球上の生命体の活動や疾患における鉄の重要性の再認識
Reappraisal of the importance of iron in the activity and pathology of living organisms on earth
 |
豊國 伸哉 名古屋大学大学院医学系研究科 病理病態学講座 生体反応病理学・分子病理診断学 教授 |
Abstract
Iron is abundant on earth, and no organisms on earth can live without iron. However, excess iron is a risk for carcinogenesis presumably via catalyzing the Fenton reaction. There are many human diseases associated with excess iron -induced carcinogenesis, and also animal models demonstrating the close association. Recently, several patterns of cellular death by programmed necrosis are recognized, among which ferroptosis is proposed in 2012. Ferroptosis may be initiated by a variety of
inhibitors of cysteine/glutamate antiporter (system Xc-), which leads to GSH depletion and lipid peroxidation. There is a huge anticipation that recently developed turn-on type fluorescent probes to detect catalytic Fe(II)would unravel novel cellular processes and molecular mechanisms, including ferroptosis and carcinogenesis.
キーワード : 触媒性 2 価鉄、発がん、フェロトーシス
1. はじめに
死因として、がんは日本において 1981 年から継続的に第 1 位、世界各国でも上位を占める。がんの原因として、喫煙、放射線、紫外線、ピロリ菌・パピローマウイルス感染など多様なものが知られるが、これらはいわば氷山の一角であり、発がんの根本原因は鉄と酸素の使用にあると私は考えるに至っている 1)。太古の海は特に触媒性 2 価鉄が豊富で、その環境で初めての生命が生まれただけでなく、いまだに鉄なしで存続できる生命体は地球上で報告がないことに着目したい 2)。鉄は周期表で d ブロックの 1 列目に位置し、イオンの価数が変化する遷移金属である。そして、脊椎動物において、酸素を運搬・貯蔵するヘモグロビンやミオグロビンのヘムの一部であり、カタラーゼやチトクロームなどの補因子としても必須なものである。鉄欠乏は貧血や発育障害を起こし、発展途上国では大きな問題となっている。しかし最近、鉄過剰は発がんリスクであるとする報告が相次ぐようになった 3)。 2008 年に公表された 1 年 2 回の定期的瀉血が内臓がん発生を 35% 減少させるという論文は衝撃的でさえある 4)。
2. 鉄のダイナミクス
鉄は、私たちの体で最も多い重金属であり、成人で約 4 g を有する。このうち 60% は、酸素を運搬するヘモグロビンのヘムとして存在する。中性では 3 価鉄イオン[Fe(Ⅲ)]の溶解性は極めて低いので(10-17 M)、鉄イオンは生体内では他の分子とキレートしたかたちあるいは 2 価[Fe(Ⅱ)]で存在すると考えられる。キレート分子としては種々のリン酸化合物、クエン酸などの低分子化合物などのほか、最近では PCBP2 といったタンパク質がシャペロンとして働くことが提案されている 5)。食餌鉄は胃の酸性環境下で可溶化し、十二指腸で吸収される。その絨毛上皮の形質膜において、消化管という外界から体内に 2 価鉄をとりこむトランスポーター(DMT1; SLC11A2)が初めてクローニングされたのは 1997 年である 6)。体内においてはトランスフェリンが全身に Fe(Ⅲ)を輸送し、余剰鉄は細胞内においては鉄貯蔵タンパク質であるフェリチンとして貯蔵される。フェリである Fe(Ⅲ)は安全だが、フェロである Fe(Ⅱ)は膜の通過に使用されるにもかかわらず、以下のようにリスクを常にはらむ。
Fe(Ⅱ)はフェントン反応の起点である。これは Fe(Ⅱ)を触媒として過酸化水素からヒドロキシラジカル(・OH)を発生する化学反応であり、酵素は関与しない。 ・OH は生物系では最も反応性の高い化学種とされ、近傍の生命分子の切断・修飾・重合を起こす。
Fe(Ⅱ)+ H2O2 → Fe(Ⅲ)+ ・OH+ OH- (フェントン反応)
酸素は究極的には体内において電子の流れをつくっていると考えられる(図 1)。 その過程で破壊性の高いヒドロキシラジカルが発生するが、生体はこれを避ける機構を有する。カタラーゼ、ペルオキシダーゼ、ペルオキシレドキシン 7)などの酵素がその役割を果たしている。
ところが、過剰鉄はフェントン反応を促進する。ラジカルは反応の相手分子を選ばないが、発がんの観点からはゲノム DNA が重要な標的である。酸化ストレスとは、1985 年に Helmut Sies により提唱された細胞や個体に関するコンセプト 8)であり、「活性酸素・フリーラジカルの負荷から、抗酸化分子・抗酸化酵素・修復酵素などによる防御・消去・修復作用を差し引いたもの」と定義される。酸化ストレスの生物学的意義に関しては、90 年代まで上記の傷害性が強調されてきたが、「軽度の酸化ストレスは細胞傷害を起こすのではなく、むしろ細胞増殖を促進する」という新たなコンセプトが確立されるに至った。これは、培養細胞に薬剤で酸化ストレスを負荷していくと、その程度が強くなるに従い順に、細胞増殖・アポトーシス・壊死という異なる現象が観察されることに基づいている。その発がんとの関係を図に要約する(図 2)。
3. 過剰鉄と発がん
鉄と発がんの関連について既知のデータは基本的に 3 種類に分類されよう。まず、ヒトがんに関する疫学データがあり、該当する主な疾患を表に示す。次は、全身の鉄貯蔵状態と発がんに関するヒトの疫学データである 9)。最後は、動物に鉄化合物を投与した際の発がん性に関するデータである。
私たちはこれまで、主として鉄化合物による腎癌とアスベストによる悪性中皮腫に関して、wild-type のラットを解析してその発がんの詳細な分子機構を明らかにしてきた。アスベスト繊維あるいは特定のカーボンナノチューブ(直径が 50 nm 程度のもの)は異物であるが、ヘモグロビンなどの鉄含有タンパク質やヒストンとの親和性が高いこと、細くて長い繊維をマクロファージが処理できないこと、そして体腔を被う中皮細胞が貪食性を有すること、これらが総合的に作用して中皮腫発がんが発症することが判明した。いずれについても、詳細は他の総説を参照されたい 1, 2)。
4. フェロトーシス(Ferroptosis)
細胞死は、壊死(ネクローシス・受動死)とアポトーシス(能動死)に大きく分けられ研究が進展してきたが、今世紀になってからプログラムされた壊死も存在することが明らかになってきた。その中で現在、フェロトーシスが注目を集めている 10)。これはフェロが使用されていることからわかるように Fe(Ⅱ)依存性の細胞死であり、erastin などの低分子投与を起点として誘導される。その後、こうした分子は Cystine glutamate antiporter (System Xc -) を阻害していることがわかり、それに伴う細胞内還元型グルタチオン (GSH) の低下、脂質過酸化へと話が広がった。鉄の触媒性を抑える desferal のような鉄キレート剤あるいは膜脂質特異的な GSH peroxidase 4 で抑制されるのも特徴である。このような状況下に岐阜薬科大学の平山祐らは Fe(Ⅱ)特異的な種々の turn-on 蛍光プローブを初めて開発した 11)。細胞内で Fe(Ⅱ)は主としてライソゾーム内に存在することがわかっているが、それは細胞の分化・がん化・傷害など諸状況で変化することが判明してきており 12)、このプローブにより様々な新知見が得られつつある。
5. おわりに
隕石の成分分析より宇宙には鉄が豊富にあると考えられており、鉄代謝は生命にとっておそらく根源的なものと考えられるが、その過剰はがんのみならず動脈硬化をはじめとする他の疾患にも関わっている可能性が高い。有効に利用されない過剰鉄が慢性的に存在する状況は生体にとって好ましくなく、日本人の健康寿命をさらに延ばすためには、年齢・性別に応じた体内鉄の適切な制御が必要であろうと考える。私は機会あるたびに 65 才までの年 2 回の献血を薦めている。
| 著者プロフィール | |
| 氏名 | 豊國 伸哉 (Shinya Toyokuni) |
|---|---|
| 所属 | 名古屋大学 大学院医学系研究科 病理病態学講座 生体反応病理学・分子病理診断学 教授 |
| 連絡先 | 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 TEL: 052-744-2086 FAX: 052-744-2091 E-mail: toyokuni@med.nagoya-u.ac.jp |
| 出身大学 | 京都大学医学部 |
| 学位 | 医学博士 |
| 専門分野 | 病理学 |
| 現在の研究テーマ | 発がん機構の解明、がん予防、鉄代謝、フェロトーシス |