液-液相分離 (LLPS) は細胞内で特定の分子が局所的に集まり、液体のような性質を持つ生体分子の凝集体(液滴)を形成する現象です。
近年、LLPS が細胞内での多くの生物学的プロセスに影響を与えることが明らかになり注目を浴びています。今回、本分野のトップランナーである白木先生とご研究室の皆様にお話を伺いました。

インタビューに参加いただいた白木研究室の皆様
(左から)白木賢太郎教授、浦朋人助教、飯島さん、中村さん、吉田さん、野本さん、亀丸さん
(取材:2024年8月19日)
液-液相分離 (LLPS) は細胞内で特定の分子が局所的に集まり、液体のような性質を持つ生体分子の凝集体(液滴)を形成する現象です。
近年、LLPS が細胞内での多くの生物学的プロセスに影響を与えることが明らかになり注目を浴びています。今回、本分野のトップランナーである白木先生とご研究室の皆様にお話を伺いました。

インタビューに参加いただいた白木研究室の皆様
(左から)白木賢太郎教授、浦朋人助教、飯島さん、中村さん、吉田さん、野本さん、亀丸さん
(取材:2024年8月19日)
白木先生)液-液相分離というと用語は難しいですが、要するに水と油が混じらないようなものです。こういう日常にありふれた現象を、細胞の中のタンパク質とつなげて考えた人がいなかったのは不思議なものです。最初の重要な報告として、2009年のマックス・プランク分子細胞生物学・遺伝学研究所のTony Hymanの研究チームのCliff Brangwynne博士らの論文があります。細胞内にあるP顆粒と呼ばれるタンパク質集合物が、液体のような特徴があるということを顕微鏡などで調べて報告しています。しかし、この論文だけではまだLLPSは注目されませんでした。
3年後の2012年に、テキサス大学 サウスウェスタンメディカルセンターのMichael K. Rosenの研究チームと、Steven L. McKnightの研究チームが独立に、LLPSに関する論文を出しています。McKnightの研究チームの加藤昌人さんはRNA結合タンパク質を取り出すとゲル状になることを発見して、これが細胞の中にあるオルガネラに似ているのではないかと気付かれました。また、Rosenの研究チームは2種類のタンパク質を混ぜると液滴ができることを発見しました。この2つの発表で、LLPSの重要性に気づいた分子生物学や細胞生物学の研究者が世界中に出てきました。それから数年間はお祭り騒ぎのように、ネイチャー誌やセル誌などの有名誌にLLPSの論文が報告されるようになりました。
LLPSが学会にはじめて登場したのは、おそらく2018年のProtein Societyです。当時アメリカで行われたProtein Societyに参加した産総研の亀田倫史さんらが帰ってきて、これはすごいと言っていました。それで日本でも研究会をしてみようということで、亀田さんが発起人となって2018年にLLPS研究会が発足しました。最初は産総研で開催して、確か80人くらいは集まりました。話せる方が当時は全くおらず、私たちの研究室だけで6人くらい発表したと思います。ちょっと面白い集まりになりましたね。
浦先生)第1回のLLPS研究会では、LLPSの基礎から応用まで内容を分担して研究室の学生みんなで発表しました。私は当時修士1年だったのですが、著名な先生方の前で緊張しながら口頭発表したのを覚えています。第1回、第2回、第3回、第4回と続き、この頃になると細胞生物学やタンパク質の構造計測などを専門とする研究者の方々など幅広い分野の人が参加して、発表するようになりました。そのあとコロナ禍が来て、対面での集まりはいったん休止となりました。

白木先生)「相分離生物学」という用語をはじめて学会で使ってみたのは2019年の蛋白質科学会・細胞生物学会の合同年会でした。このシンポジウムは部屋に入りきれないほど人が集まり、横の壁を抜いてもらって対応したほどでした。当時は個人的な研究会などにたくさん呼んでいただいて、半年でおそらく30回くらいは講演して議論したと思います。同時期に『相分離生物学』の教科書を出版していますが、1年後には『相分離生物学の全貌』と名づけた分厚い本を出しました。これは当時、講演会場や居酒屋でディスカッションした人と79本のトピックスとしてまとめた専門書です。ふつう専門書は既に行った結果を書くものですが、この本はこれから何をやろうかということも沢山書いてあり、かなり面白いです。
白木先生)これからのLLPS研究の鍵を担うのは、何より計測機器の開発です。タンパク質を調べる計測機器はこの半世紀で高性能化してきました。原子レベルでマイクロ秒やナノ秒などの時間分解能でタンパク質を理解できるようになり、分子生物学や構造生物学、生化学が進歩してきました。それでかえって、マイクロメートルぐらいで、ゆっくりした動きを染色せず非破壊で測定できる機器の開発がなかなか進みませんでした。今はLLPSにピッタリの計測法は光学顕微鏡くらいしかないというが現状です。そのような中で、Hymanらの研究チームは細胞内の液滴を観察しようと思ったのですから素晴らしいと思います。今の我々はよく知っていますが、例えば酵素の液滴を作らせると、酵素活性が大幅に上がるようなことがあります。こういう視点は、個々の酵素をいくら調べてもわからないことです。酵素が液滴になるということなど生化学の教科書にも書かれていない視点で、だから誰もやろうと思わなかったのです。
浦先生)私は液滴を作らせると酵素反応が100倍ほど高くなるという現象を発見して、メカニズムを調べていますが、これからは液滴の中の物理化学的な特徴を評価する必要があると考えています。例えば、液滴内部のpHやクラウディング効果、粘度、水分量などを計測して、見積もる方法がこれまでにも報告されています。これらの方法は各論的に開発が進んできたものですが、例えば、液滴内のpHを調べるにはこの蛍光分子を使えばいいなどの標準的な方法をつくることで、液滴の生物学的意義を定量的に議論できるようになると思います。今はまだ標準的な方法が確立されていない段階です。
吉田さん)液滴の大きさも重要だと思います。顕微鏡で観察するために、数十マイクロメートル程度の大きさの液滴をつくらせることが多いですが、これは細胞と同じくらいの大きさです。細胞内にはもっと小さい液滴があるはずで、プロテオームの約2割が数百ナノメートルの液滴を作る、といった報告もあります。現在の顕微鏡では解析ができないような小さなサイズの液滴を詳しく調べると、面白い現象が出てくると思います。
白木先生)液滴とはどういうものかという質問をよく受けますが、再現は意外に簡単です。同仁化学さんからもLLPS関連の製品を出されますが、例えば、「相分離液滴 作製・観察スターターキット」のように、BSAのようなありふれたタンパク質に高濃度のPEGを入れるだけで液滴ができます。例えば、実験科学になじみのない計測機器の研究者や顕微鏡の専門家も、このようなキットで液滴を見てみると、雰囲気がつかめると思います。
「相分離液滴 作製条件検討キット」も複数のクラウディング剤や緩衝液が入っていますが、実験してみるとちょっとした条件の違いで液滴ができやすかったり、できにくかったりがあると思いますね。タンパク質の立体構造などは安定で、イオン強度が多少変わっても変わらないですが、液滴はできたりできなかったりしますし、液滴になってもゲルっぽかったりだんだん固くなったりするような変化も起こります。取扱説明書を読ませてもらいましたが、こういう液滴の性質を丁寧に調べられていて、論文にまとめても良さそうなくらいですね。
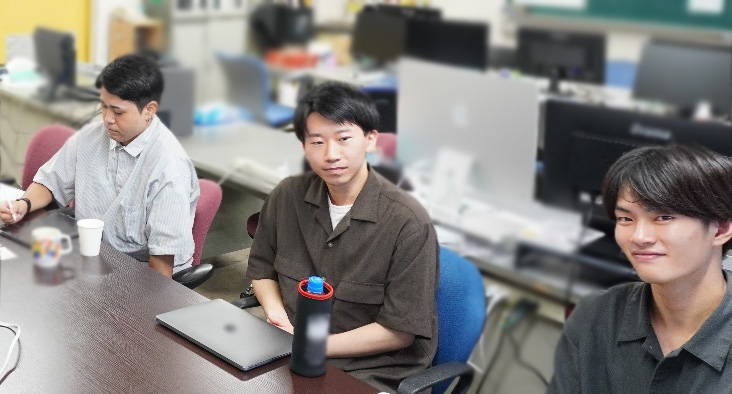
野本さん)酵素工学や医学の分野でますます注目されると思います。特に、医学の分野では「相分離創薬」というLLPSの状態制御に基づいた薬の開発が検討されているみたいです。また、アカデミックな方面ですと、生命機能を人工的に作製する合成生物学の分野にLLPSの研究が貢献できるかもしれません。
飯島さん)私も医薬だと思っています。高濃度製剤などや、薬のDDSなどの応用が社会的にも需要があると思いますし、学術的にもまだ未開拓の部分があるかもしれません。生きた細胞の中での現象を観察することを考えると、in vitroとin vivoとのギャップを埋める技術が必要になると思います。
亀丸さん)私も主に医薬分野だと思います。アミロイドβの例を挙げると、どの薬剤が液滴形成を抑制するのか、はたまた形成された液滴を溶解するのかを実験的に調べるためのin vitro試験など、ますます需要が高まってくると思いますね。
浦先生)特定の立体構造をもたない天然変性タンパク質の機能や、タンパク質の線維化との関連が報告されている疾患に関する研究が、LLPS分野の一番のホットトピックであると思います。それ以外の面では、代謝にかかわる酵素群も面白いと思っています。代謝酵素は、特定の立体構造をもつタンパク質として古くから研究されてきましたが、LLPSによってその活性が調節されることがわかりつつあり、代謝工学の分野でも論文が出てきています。そもそも立体構造を持つタンパク質を結晶化させるときに、LLPSのような状態が観察されることは、タンパク質研究者の方々にとっては珍しくないことだったと思います。調べてみると案外その状態では酵素の活性が変化しているかもしれません。
吉田さん)医薬系以外だと、生命起源や原始地球を理解するヒントとして相分離が注目されていると思います。液滴内にはRNAを隔離できますし、例えば原始地球の環境にもありえた分子で液滴を作ると、液滴内は化学反応が促進されるような反応場となる、といった研究もあります。
白木先生)確かに生命の起源の研究者たちも、相分離に注目していますね。これまでコアセルベートのように物質が集まるのは知られていましたが、単に物質が集まるだけではなくそこに機能を追加できるという見方はなかったと思います。あとは亀丸君の話にあった視点の転換も面白いです。アルツハイマー病の原因とされてきたアミロイドなどは、その手前にある液滴が本当の毒性の主体かもしれません。この相分離の状態を抗原とした抗体を開発するといいと思うんです。そのためには、相分離だけでも足らなくてAIが必要になります。

話が少しそれますが、AIはこれからタンパク質の研究にも不可欠になっていきます。液滴をうまく取り出して、マウスに注射して抗体を作らせるのはほぼ不可能です。液滴は溶液条件によってすぐ壊れたり変化したりするからです。こういうところにこそAIが活用できると思います。AlphaFoldが登場して、今では実験するまでもなくタンパク質の構造を明らかにできるようになっています。全部のタンパク質の構造を解いてデータベースに入ったのが2022年のことですが、2024年になると抗体と抗原やDNAと結合タンパク質の複合体など、学習データがほとんどなかったものでも解読できるようになっています。こういう進歩を考えると、液滴の状態をAIに考えてもらい、その液滴と相互作用する抗体なども開発できるようになると思います。
白木先生)相分離の概念が出てきて、それが広がっていったのをタイムリーに経験できたのはすごく面白かったと思いますね。これからも予想外の広がりがあると思います。僕の場合もLLPSでいろんな発見があって、代謝のような複雑な反応がどうして混線せずに進んでいくのかとか、細胞内にそもそもなぜこれだけ高濃度の物質があるのかとか、ようやく説明できるようになりました。死ぬ前に細胞がちょっと膨らむ理由とか、高濃度のATPが細胞内にある理由とか、細胞と分子の間にあるいろんな現象が新たに説明できるようになると思います。あとはアルツハイマーの抗体薬が20年以上もかけてどうして作れなかったのかも、さきほど話したように納得できました。LLPSの視点がなかったからですね。
浦先生)LLPSが試験管内と細胞内のミッシングリンクとして認識され、うまく説明できる現象が増えつつあると思います。一方で、創薬への展開についても関連しますが、実際にLLPSという現象が見つかって何が良いのか、何をできるようになるのかについて考える必要があります。これまで注目してきた“分子”を対象とした視点と何が明確に違うのかという点に答えを出すためには、LLPSの物理化学的特徴を計測して評価し、議論を進める必要があります。また、細胞内を観察したからこそLLPSの発見につながったと思いますが、将来的には細胞生物学の分野を飛び越える発展も必要だと思います。スフェロイド、オルガノイド、個体等でもLLPSの計測と制御法の確立へと繋げていくことが生物学全体としてLLPS研究が目指すところだと思います。最後に、個人的には、分子シミュレーションでLLPSの形成や成熟の過程が再現できるようになればかなり面白いと思います。そうなるとやっと僕らの実験結果の意味も分かってくるというか、現在は計算コスト的にたどり着けないので、実験的に調べるしかない現象が沢山あります。
吉田さん)液滴は細胞内に普遍的に存在していて、例えば液滴を作ることで酵素を活性化する、というのは生命が獲得した機能だと思います。そのような酵素活性化の仕組みを取り出して工学として利用するのも良いのではないでしょうか。
白木先生)吉田君のいうように工学利用はインパクトがありますね。薄い緩衝液に入れるだけでは酵素の本来の働きを引き出せていない可能性があって、液滴を作らせることで本来の状態を取り戻すことができるのだと思います。吉田君や浦先生の研究テーマとも関連しますね。
野本さん)生命科学や酵素工学以外ですと、材料科学の分野でLLPSの研究が関われるのではないかと思っています。生体分子を扱う企業の方々とお話しをすると、タンパク質の作製はコストがかかり、作ってもすぐ壊れるということから、タンパク質は扱いが難しい分子だという話をよく聞きます。タンパク質を他の有機・無機材料みたいに簡単に扱えるようにするために、LLPSの視点材料科学の分野でもブレイクスルーになればと期待しています。
中村さん)これからAI技術が発展していき、AIと人間の共存がより求められると思います。既に、タンパク質やDNA等の構造や相互作用を予測するAIも開発されています。もう、あと数年で液滴を作るタンパク質や分子等を予測して実験系を提案してくれるツールなども台頭するのではないでしょうか。AIを最大限に活用した我々の強みというものをしっかり確立しないといけないとも思います。
白木先生)中村君の話どおりAIの影響は本当に大きいですね。最初にAlphaFoldが出てきたとき、構造生物学は終わりなのかと思っていたのですが、専門家と話をするとネガティブなことではないようです。タンパク質の構造をAIに探させて、オリジナルな構造を持ったタンパク質が出てきたらそれを対象に実験をしているそうです。手間のかかるスクリーニングをAIに任せて面白いところを人間が実験するようなことでしょうか。面白い時代がはじまっていると思います。
浦先生)LLPSの特徴と酵素の特徴、活性化率などのデータが数多く揃えば、それらを学習データとして今後AIを活用可能になるかもしれないですね。
白木先生)そうだと思います。LLPSはおそらくLLPSそのものが大事なのではなく、そこにある特殊な相互作用を主役にして考えるのが大事だと思います。例えば、尿素の粉末と塩化コリンの粉末を混ぜると液体になります。こういうのを深共晶溶媒といいますが、こういう液体を作らせて眺めていると、細胞中のタンパク質というのは水に頑張って溶けているようなイメージではなく、タンパク質が非常に馴染みやすくなるような全体の場ができているのだろうという気がします。相互作用を主役に、いろいろ考え直すとさらに本質に迫ることができるのではないでしょうか。それは分子を見て育ってきた我々の世代の研究者には想像しにくく、いわゆる相分離ネイティブである20代の研究者にはできることかもしれません。
同仁化学)貴重なお話をありがとうございました。皆様に語っていただいたLLPS研究は、生命科学の新たな可能性を広げる重要な分野であり、疾患メカニズムの解明や新たな治療法の開発、さらに酵素やタンパク質、材料科学、AIとの応用の可能性などが今回のインタビューで知ることができました。本分野の研究が進み、先生が強調された相互作用の役割が明らかになることで、今後さらに多くの生物現象が解明されていくと感じました。我々も本分野の発展にお役に立てるよう研究開発を続けて参ります。本日は長時間に渡り誠にありがとうございました。
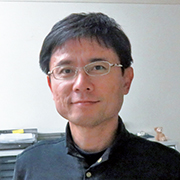
白木 賢太郎 筑波大学数理物質系 教授
しらき・けんたろう/大阪生まれ。1999年大阪大学大学院理学研究科修了、理学博士取得。
北陸先端科学技術大学院大学助手、筑波大学物理工学系助教授を経て2016年から現職。専門はタンパク質溶液学、相分離生物学。著書に『相分離生物学』(東京化学同人)、『相分離生物学の全貌』(東京化学同人)、『相分離生物学の冒険』(みすず書房)。